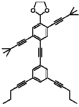氷で遊んでみよう!
ウエストポーチ
1. はじめに
簡単なモデルを用いて氷の誘電率を計算してみました。
2. 無秩序なプロトン
2.1. 氷の結晶構造

(図1)氷の結晶構造。球は酸素原子、黒線は水素結合を表す。
氷の結晶では、酸素原子がダイヤモンドを構成する炭素原子と同様な配置をとっています(図1)。ある1つの酸素原子(赤い球で表されているものがわかりやすい)に注目してみると、隣接する酸素原子が4個あることがわかります。隣接する酸素原子同士は水素結合で結ばれています。つまり、負の電荷を帯びている酸素原子は正の電荷を帯びたプロトン(水素原子のことです)を仲立ちにして結合しています。「仲立ち」というと、なんとなくプロトンが2つの酸素原子のちょうど真ん中にあるような気がしますが、実際はそうではなく、プロトンはどちらか一方の酸素原子に寄っています。というわけで、ビシッと整列している酸素原子とは異なり、プロトンはけっこう自由に配列することができます。では具体的にどれくらい自由に配列できるのか、次節で見ていきましょう。
2.2. プロトンの配置は何通り?その1
プロトンの配列にはかなり自由があることを前節で述べましたが、それでもいくつか制限があります:
ルール①: 酸素原子間の結合には必ずプロトンが1つだけある
ルール②: 1つの酸素原子はちょうど2つだけのプロトンに寄られている
これらの制限を念頭に入れて、プロトンの配置が具体的に何通りあるのか、$N$個の水分子がある場合で考えてみましょう!
まずは水素結合に注目します。ルール①によると、1本の水素結合が取りうる状態はプロトンが一方の酸素原子に寄るか他方の酸素原子に寄るかの2通りだけがありえます。水分子が$N$個あれば水素結合はその2倍、つまり$2N$本ある(1つの水分子は4本の水素結合を持ち、かつ1本の水素結合は2個の水分子で共有されているため)。よって水素結合全体がルール①を満足しながら取りうる状態の数は$2^{2N}$。
次に酸素原子に注目します。1つの酸素原子は4本の水素結合を持っていますが、そこにある4つのプロトンが自由に配列できたとすると、取りうる状態の数は$2^4=16$通り。これら$16$通りのうちルール②を満たすものは$6$通りなので、1つの酸素原子がルール②を満足する確率は$6/16=3/8$(図2)。よって酸素原子が全てルール②を満足する確率は$(3/8)^{N}$ (Hollins(1964)によると、このステップでけっこう大胆な近似を行っています)。

(図2)酸素原子の16個の状態
以上より、可能なプロトンの配列は$2^{2N}\times (3/8)^N=(3/2)^N$。
2.3. 結晶構造の見方を変えてみる
ここで、氷の結晶構造を今一度見返してみましょう。

(図3)氷の結晶構造と切断面
第2章で使った図を、切断面上に酸素原子が乗るようにしながら斜めに切ってみました。切断面の間隔は広い・狭い・広い・狭い...と交互に現れそうです。間隔の狭い切断面に挟まれている酸素原子のまとまりを、以下では「層」と呼ぶことにします。氷の結晶構造を層ごとに分けて見たのが次の図4です。

(図4)層ごとに見た氷の結晶構造
層と層の間の結合は鉛直に、層の内側にある結合は斜めに伸びています。
2.4. プロトンの配置は何通り?その2
さて、今度は層に注目ながら状態数を数え上げていきましょう!
まずは問題を具体的に設定していきます。今回考える氷は$2M$個の酸素原子を含む層が$L$枚重なった構造をしています(したがって水分子の数数は$N=2ML$)。氷の上面には$M$個の水分子が並んでいることになります。さらに、最上段の層が上向きに伸ばしている水素結合上のプロトンのうち下向きに配向しているものを$Mp$個に固定します。

(図5)氷の層構造の模式図
まずは最上段の層に注目します。鉛直上向きに伸びている水素結合上のプロトンは、下に寄っているものが$Mp$個、上に寄っているものが$M(1-p)$個あるという条件が課されていました。この条件と上側の酸素原子がすべてルール②を満足しなければならないことから、層の内側にある斜めに伸びた$3M$本の水素結合上のプロトンは、$M(2-p)$個が上側、$M(1+p)$個が下側に寄らなければなりません。さらに下側の酸素原子がすべてルール②を満たすために、鉛直下向きに伸びた水素結合上のプロトンは、$Mp$個が上側、$M(1-p)$個が下側に寄らなければなりません。
同様の議論を第2層目、第3層目、...に適用していくことで、鉛直方向に伸びる水素結合上のプロトンが上寄りは下寄りかの比率は層によらず$(1-p):p$になることがわかります。ところで、話は少しそれますが、この氷の電気分極$P$は
\begin{equation} P=c\mu (p-(1-p))=c\mu (2p-1) \end{equation}($\mu$は水分子の双極子モーメントの鉛直方向の大きさ、$c$は水分子の数密度)で表されます。
次に、2.2.でのやり方を真似て1つの層が取りうる状態の数を求めます。鉛直上向きに伸びた水素結合の配向は固定されているとして、斜めに伸びた水素結合と上側の酸素原子のすべてがルールを満たしているようなプロトンの配置は$3^N$通り。このときに下側の酸素原子1つがルール②を満たすのは、斜めに伸びた水素結合から1個か2個のプロトンに寄られている場合なので、確率は $3\times (\frac{2-p}{3})^2\times \frac{1+p}{3}+3\times \frac{2-p}{3}\times (\frac{1+p}{3})^2=\frac{-p^2+p+1}{3}$。よって、1つの層が取りうる状態数は$(\frac{p^2+p+1}{3})^M$であり、従って氷全体が取りうる状態の数は \begin{equation} W(p)=(\frac{p^2+p+1}{3})^{ML} =[9/4-(p-1/2)^2]^{N/2} \end{equation} という結果が得られました。
3. 統計力学的な話
3.1. 残余エントロピーについて
2.2.節では、プロトンの配向について可能な状態数が$W=(3/2)^N$であると求まりました。このときの$k \ln(W)=Nk\ln(3/2)$ ($k$はBoltzmann定数)は、氷の温度を絶対零度に近づけてもなお残るエントロピー、つまり残余エントロピーの値とよい一致を示します。これはPauling(1935)によって考案されたやり方で、物理化学の教科書(例えば参考文献[3])などでもよく見かけます。
ところで、2.4.では結晶の電気分極が指定されているという条件のもとで、状態数が$W(p)=[9/4-(p-1/2)^2]^{N/2}$であると求まりました。これを基にして残余エントロピーの理論値$k\ln(\sum_p W(p))$を求めるには$\sum_p W(p)$を計算しなければいけなさそうですが、$Nが大きいと$W(p)は$p=1/2$の一点で鋭いピークを示すはずなので、結局は$\sum_p W(p)\approx W(1/2)=(3/2)^N$としてしまってもよさそうです。実際、 \begin{equation} (3/2)^N< \sum_p W(p) < M (3/2)^N \end{equation} \begin{equation} \ln(M{}_M C_{M/2} (3/2)^N)\approx N\ln(3/2)) \quad (N\rightarrow \infty) \end{equation} が成り立ちます。よって$k\ln(\sum_p W(p))=Nk\ln(3/2)$、つまり2.2.の方法と全く同じ表式が得られます
4.2. 氷の誘電率の計算
氷に弱い電場$E$を下向きに印加する場合を考えます。ここで、系のエネルギーは \begin{equation} U=-[p-(1-p)]\mu E N=-N\frac{EP}{c} \end{equation} で与えられると仮定します。 エネルギーの低い状態が実現しやすいことを反映するために、各状態の実現確率を$\exp(-U/kT)$で重み付けをすることで(カノニカル分布)、$P$の確率分布$f(P)$は次のような形になります。後で調べて分かったのですが、このような手法で氷の誘電率を考察するのは、例えばHollins(1964)によってなされてなされていました。
最後までお読みいただきありがとうございました。
参考文献
[1] Jacob N. Israelachvili (2013)『分子間力と表面力』(大島広行訳) 朝倉書店
[2] 中村哲, 須藤彰三『電磁気学』朝倉書店
[3] 小川桂一郎, 小島憲道 編 『現代物性化学の基礎 第3版』講談社
[4] Hollins,G.T. (1964). Configrational statics and the dielectric constant of ice. $Proceedings of the Physical Society,84$(6),1001-1016. doi:10.1088/0370-1328/84/6/318
[5] Pauling,N. (1935). The Structure and Entropy of Ice and of Other Crystals with Some Randomness of Atomic Arrangement. $Journal of the American Chemical Society. 57$(12), 2680-2684.