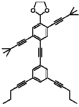サイクリックボルタンメトリーの基本的な測定
氏田瑞葉
私は所属する研究室で電気化学測定をよくおこなっている。測定方法は様々だが、たいてい一番初めに測定するのはサイクリックボルタンメトリー (Cyclic voltammetry, CV) である。これから、この電気化学測定の基本といえるCVについて紹介する。ただ、測定結果の理論式に基づいた説明は多くの書籍やオンラインで閲覧可能な文献で既に詳しくなされているので、この記事では実際的な測定方法について多く記す。
CVとは溶液の系内で起こる酸化還元反応を観測する測定方法である。では、この測定により具体的にはどのような情報が得られるのだろうか。測定する物質そのものに着目すると、酸化還元電位や酸化体・還元体の安定性などである。また、酸化還元の反応に着目すると、反応の可逆性や反応速度などである。これらの情報は測定物質を化学的に酸化還元させるときや化学電池として利用する場合などに重要となる。
CV原理とセットアップを簡単に紹介する。CVでは一定の変化率で時間変化する電圧を系に印加してそのときに流れる電流を測定する。より具体的には、測定中に印加する電圧が測定する物質の酸化電位よりも大きくなれば電極表面において測定物質の酸化反応が起こって電流が流れる。逆に物質の還元電位よりも小さくなれば、還元反応によりこの場合も電流が流れる。このように測定物質の酸化還元反応を観測するのである。CVのセットアップの概略図を図1に示す。

図1. CVのセットアップ
系に対する電圧の印加と生じる電流の測定はポテンショスタットと呼ばれる装置でおこなう。この装置は卓上プリンター程度の大きさで持ち運びも簡単である。測定には3種類の電極を用いる。対極、参照極、そして作用極である。参照極は一定の電位をもつ電極で、参照極を基準として作用極の電位を変化させる。電圧を印加して流れる電流を測定するだけであるから電極はこの参照極と作用極の2本で十分に思われるかもしれない。なぜ3本目の電極の対極が必要なのかというと、簡潔な答えとしては測定中に電極反応が起こるからである。もし参照極と作用極だけであれば、電極反応が起こった時に参照極に電流が流れてその電位が変化する。基準となる電位が変化したのでは正確に電圧を印加することができない。そこで、3本目の対極を導入して対極と作用極の間に電圧を印加することで電流が作用極と対極の間でのみ流れるようにして参照極の電位を常に一定に保つのである。作用極と参照極の間の電位差は常に測定されていて、それが設定した通り変化していくように対極と作用極の間に適切な大きさの電圧を印加するのである。このように3種類の電極を使って測定をおこなうやり方を三電極法と呼び、電気化学測定ではたいてい用いられる方法である。次に電極とポテンショスタットの接続を見ると、作用極に2本の導線が接続されているのに気づくだろう。一方の導線は対極との間に流れる電流を測定するための回路につながっており、もう一方は参照極との電位差を測定する回路につながっている。2本必要なのは電流の測定方法に由来する。ポテンショスタットでは、正確に定まった抵抗値をもつ抵抗器に電流が流れるときに降下する電圧から電流値を測定している。いわゆる抵抗シャント方式である。実際の作用極の電位と抵抗器を含む回路の電位は異なるので、作用極と参照極の間の電位差を測定するための回路が必要となって導線も2本使うのである。このような測定方法は四端子法と呼ばれている。
3種類の電極について詳しく説明する。参照極は、水溶液の測定ではAg/AgCl電極が一般に用いられる。液絡部を先端に持つガラス製の細いチューブに飽和KCl水溶液とAgClで表面が覆われたAg電極が入っており、電極の先だけ導線と接続できるように外に出した状態で密封されている。保管の際は液絡部が保存液 (飽和KCl水溶液) に浸るようにする。有機溶媒中の測定ではAg/Ag+電極がよく使われる。私の所属する研究室では、内部液および保存液としてヘキサフルオロリン酸テトラブチルアンモニウム (TBAPF6) とAgNO3をそれぞれ0.1 Mの濃度で含んだアセトニトリルを用いたものが最も一般的である。TBAPF6は水と反応してフッ化水素を生じるので、誤って水溶液測定に用いないように注意している。またこれらの参照極は液絡部が汚れやすい。先端だけの少々の汚れなら測定にほとんど影響しないのだが、液絡部全体がひどく変色したものを使ったときは酸化還元電位が0.1 V近くずれて測定された。作用極はグラッシーカーボンをよく用いる。作用極表面が汚れていると正確な測定ができないので、使用前にアルミナを含む研磨剤を使ってフェルトで磨く。八の字を描くように20回を目安に磨くよう教わった。対極は流れる電流量を制限しないように表面積が十分に広いものを用い、材質は白金であることが多い。表面積を少しでも増やすためにバネ状にねじってあったり先が巻いてあったりするものもある。
いよいよ実際の測定についてである。測定者は電圧の掃引速度や範囲、掃引方向を設定することができる。CVの特徴の一つは電圧の掃引方向を変えながら連続的に測定できることである。言い換えれば、設定した範囲の間で電圧を何度も上げたり下げたりして測定できるということである。電圧の掃引方向が同じである区間1つを1セグメントと数える。信頼できるデータを得るために通常は4セグメント以上の測定をする。電圧の掃引の例を図2に示す。例では4セグメント目まで測定しており、掃引速度は10 mV/sで-0.5 Vから1.0 Vの範囲を掃引している。

図2. 電圧の掃引の例
うまく測定をおこなうには、電圧掃引に関わる各パラメーターの設定が重要である。掃引速度についていえば、私は酸化還元を示す有機化合物を測定することが多いのだが、基本的には10 mV/s、ゆっくり掃引するときは1 mV/s、速く掃引するなら50 mV/sや100 mV/sに設定している。もちろん掃引速度はどのような物質を測定するかによって変わってくるが、私の所属する研究室ではこのぐらいの掃引速度で測定している人が多い。掃引範囲は測定物質の酸化還元反応が含まれるようにとる。しかし、一度も測定したことがない物質の場合は酸化還元の起こる電位の見当がつかないので、100 mV/sなどの速い掃引速度で広範囲を測定しておおよその酸化還元電位を確かめるとよい。測定に使う溶液としては、測定したい物質1 mMと支持電解質 (KCl、TBAPF6など) 100 mMを含むものを使うことが多い。撹拌などはせず静止溶液に対して測定をおこなう。実際のCVの測定結果のプロット (ボルタモグラムという) を紹介する。図3のボルタモグラムはフェノチアジンのアセトニトリル溶液を測定したものである。

図3. 1 mMのフェノチアジンと100 mMのTBAPF6を含むアセトニトリル溶液のボルタモグラム。掃引速度は10 mV/s、溶液温度は15 ℃で4セグメント測定。開始電位と下限電位は0 Vで上限電位は1.0 V。
開始電位と測定範囲の下限が一致していれば、ボルタモグラムは2セグメントでちょうど1周する。これが”サイクリック”ボルタンメトリーと呼ばれる由来である。図3では4セグメント目まで測定しているので、ボルタモグラムとしては2周している。図4は1セグメント目が終わったときのボルタモグラムである。

図4. 1セグメント目のボルタモグラム。0 Vから1.0 Vへ掃引。
1セグメント目の間に測定溶液ではどのような現象が起きているのだろうか。0.3 V付近にピークが1つ生成しているが、これはフェノチアジンが酸化されてラジカルカチオン体となる酸化反応を示すものである。掃引を始めたばかりの0 V付近ではフェノチアジンは電荷をもたない中性体として存在する。やがて作用極の電位が上昇すると、フェノチアジンのもつ電子の1つは作用極へ移動した方がエネルギー的に安定となる。作用極がフェノチアジンに対して酸化剤として働くようになるのである。作用極へ移動した電子はそのまま対極へと流れるので電流として観測される。酸化反応が始まった直後は作用極の近傍に中性体のフェノチアジンが十分量存在するので、電位が上昇するほど酸化の速度が上昇し大きな電流が流れる。ところで、作用極へのフェノチアジン中性体の供給は溶液中の物質移動の主な3種の形態 (拡散、対流、泳動) のうち拡散によってしかなされない。なぜなら溶液は撹拌されず一定温度で、かつ電極周りで電位差が生じてはいるものの多量の電解質を加えているため泳動も起こらない。その結果、フェノチアジン中性体の酸化が作用極周りで進行していくと、酸化反応が拡散移動より十分に速ければやがては作用極付近がラジカルカチオン体ばかりになって中性体が欠乏する。そうして電流値は減少に転じる。この一連の現象が0.3 V付近で観測されている。0.5 Vあたりまでは電流の減少が続く。特に、酸化還元ピークを過ぎて約0.1 V以上離れると (つまり図の0.4 ~ 0.5 Vの範囲)、流れる電流値は物質の拡散速度に依存するようになるといわれている。このような電流を拡散制御電流と呼ぶ。0.5 Vを過ぎると再び電流値が上昇し0.7 V付近にもう1つピークが生じている。これはラジカルカチオン体がさらに酸化されてジカチオン体となる反応が観測されているのである。ラジカルカチオン体の生成によるピークと同様に、電位の折り返し点の1.0 Vにおいて作用極付近には多量のジカチオン体が存在している。電位が1.0 Vに達すると掃引方向が反転する。図5に2セグメント目の終わりまでのボルタモグラムを示す。

図5. 2セグメント目までのボルタモグラム。1セグメント目の後、1.0 Vから0 Vへ掃引。
1.0 Vから電位を下げていくと、0.6 V付近に下向きのピークが生成する。これは1セグメント目と反対に、ジカチオン体が還元されてラジカルカチオン体を生成する反応を示している。また、0.25 V付近の下向きピークはラジカルカチオン体から中性体への還元によるものである。今回の例ではどちらの反応でも還元反応のピークが見えているが、物質によっては酸化ピークが見えても還元ピークが見えないことがある。そのような現象が起こる原因としては、生じた酸化体が不安定で逆方向の掃引をする前に酸化前の状態に戻っている、という場合が多い。学生実験のような教育的な実験では、酸化還元をともなう不可逆な化学反応が起こっている、という場合もある。CVにおいて、ある酸化還元反応が可逆であるならばその反応についてのボルタモグラムが点対称な形状をとる。さらに、可逆な酸化還元反応では酸化ピークを与える電位と還元ピークを与える電位の平均が標準酸化還元電位 (E1/2) となる。ただし実際のところ、ボルタモグラフからE1/2を見積もろうとしても複数の酸化還元反応が近い電位で起こっていて電流ピークが重なっていたり、電流ピークがブロードであったりして難しいことも多い。E1/2を測定するにはスクエアウェーブボルタンメトリー (Square wave voltammetry, SWV) という別の測定方法の方が簡単である。
CVの測定の流れは以上のようなものである。だが、実際の測定では様々な要因でうまく測定できないこともしばしばある。よく起こるのが、何らかの電流は測定されているものの明らかにプロットがおかしい、というものである。主要な原因をいくつか挙げる。1つはポテンショスタットの測定感度が高すぎることだ。ポテンショスタットの機種によっては掃引速度が特定の値よりも大きいと自動感度調節がおこなわれず手動で設定しなければならなくなる。このとき感度を高くしすぎていると大きな電流は測定できないので、そうした電流が流れている間は水平なプロットが引かれることになる。エラーとして「オーバーフロー」などと表示されるのだが、表示は小さくすぐには気づかないことも多い。ただ、このケースでは測定感度を低く設定すればよいだけなので再測定の手間は少ない。2つ目の原因は短絡である。作用極と対極が溶液中で接触していたり、電極と導線を繋ぐクリップどうしが接触していたりして起こり、異常に大きい電流が流れるのですぐにわかる。小さい電解セルを使って測定していると特に起きやすい。注意深くセットアップをしていてもよく起こるので、測定は時間に余裕をもっておこなうのがよい。3つ目の原因はやや稀だが電極そのものの不具合である。特に参照電極の劣化によることが多い。私が経験したのは液絡部の汚染と内部液の蒸発である。液絡部が汚れていると酸化還元電位が大きくずれ、内部溶液が枯れているとなめらかなプロットが引かれなくなる。いずれも参照電極自体を作り直すことになるので測定は別の日にまわすことになる。また、作用極の研磨不足によっても起こるらしいのだが実際にはまだ見たことがない。最後は溶媒の電位窓の影響だ。例えば溶媒として水を用いる場合、およそ+1.2 V以上または-1.0 V以下の電圧を印加すれば水の電解が起きて急速に電流値が大きくなる。したがって、水溶液中ではこの電位窓の間で酸化還元反応を起こす物質しか測定できない。主要な原因を4つほど紹介したが、この他にも測定物質の性質に起因する場合というのもある。いずれにせよ、測定がうまくいかないときは測定する系とセットアップをよく見直すことで改善が見こめる。